今週に入ってから一段と寒さが増してき、年の瀬を感じる今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか?
外来でもインフルエンザの患者さんが増加しており、ニュースでも先週あたりから患者数が増え、この年末年始が一番患者数が増加するとも言われています。
当院でも、感染対策の一貫として12月23日から面会制限がはじまりました。
・面会はご家族のみ
・高校生以下の方の面会は原則禁止
となっています。
インフルエンザの予防に関しては、予防接種・手洗いうがい・マスク着用・規則正しい生活や人混みを避けること等言われていますが、20分に1回程度水分補給を行うことも効果的と言われています。
理由としては、インフルエンザウイルスが、のどや鼻の粘膜にある乾癬部分に到着してから細胞内に侵入するまでに、最速で20分と言われています。そのため、20分おきに水分補給をすることにより、感染部分についているウイルスを洗い流すことが流すことができ、消化器官内にウイルスが入ることで分解され、感染増殖をすることがなくなるとのことです。
良ければ感染対策の為に、試してみて下さい。
寒い日が続きますが、感染対策を行い、元気に年を越して頂けばと思います。
医療福祉相談室 Pooh

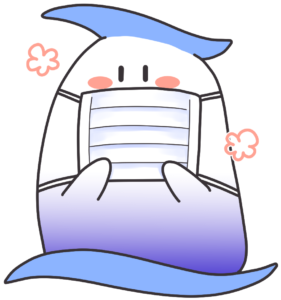
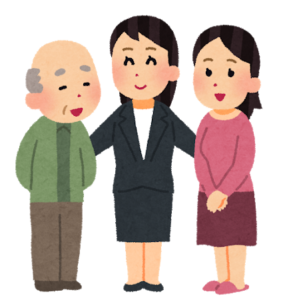 自然災害のみならず、突然の疾病や怪我によっても当たり前の日常生活が送れなくなります。
自然災害のみならず、突然の疾病や怪我によっても当たり前の日常生活が送れなくなります。



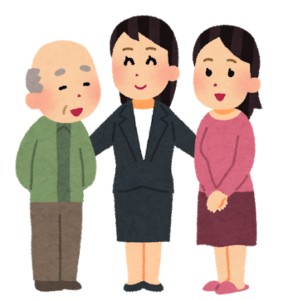



 そこで気になったのは、暗記方法の一つ、「シンクロ・マッスル学習」という勉強法。
そこで気になったのは、暗記方法の一つ、「シンクロ・マッスル学習」という勉強法。
