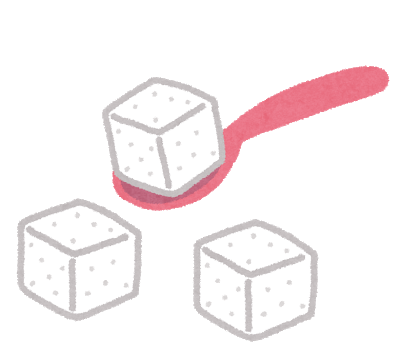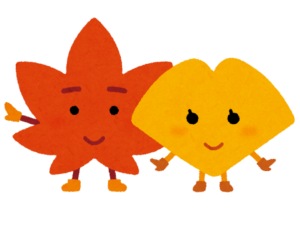1月14日にNKH本局ディレクターT氏の電話取材を受けました。番組「あさイチ」で昆布をとりあげるが、摂り過ぎによる甲状腺機能低下の可能性について調べている時に、2015年10月20日投稿の当ブログの記述を見つけたからとのことでした。( 当院ブログ「昆布の摂り過ぎによる甲状腺機能低下」 )
1月14日にNKH本局ディレクターT氏の電話取材を受けました。番組「あさイチ」で昆布をとりあげるが、摂り過ぎによる甲状腺機能低下の可能性について調べている時に、2015年10月20日投稿の当ブログの記述を見つけたからとのことでした。( 当院ブログ「昆布の摂り過ぎによる甲状腺機能低下」 )
30分あまりの電話取材でしたが、ヨウ素の必要量、日本での食事の一般的なヨウ素摂取量、過剰と思われる量、過剰摂取で異常が起こるのは10%程度の頻度、甲状腺機能に何らかの変化がある人が要注意、日本人では潜在的な甲状腺機能障害が高頻度でみられることなどを伝えました。翌日以降、テレビ録画して確認したところ1月16日の「あさイチ」で富山市民の皆さんが色々な形で昆布を美味しく沢山摂っているとの特集があり、昆布の有効成分について解説がありました。ヨウ素含有量については触れていませんでしたが特集の最後のところで、「昆布の摂り過ぎでごく一部の人に甲状腺機能低下がおこることがあるので注意しましょう」と結ばれていました。富山市民の皆さんのヨウ素摂取量はかなり過剰と思われる映像でしたが、ヨウ素の影響を少なくする代謝機構が備わっているのかもしれません。
さて、甲状腺機能(甲状腺ホルモン値)は正常範囲であるのに、甲状腺刺激ホルモン(下垂体前葉から分泌されます TSHと略します)が、基準以上に高値(潜在性甲状腺機能低下症)、基準以下の低値(潜在性甲状腺機能亢進症)の状態の方をかなりの割合で見かけます。治療が必要かどうかについて悩ましい状況です。
すみれ病院(大阪市)名誉院長の浜田 昇先生は「甲状腺疾患診療パーフェクトガイド(診断と治療社 2014年改訂第3版)」において以下のようにまとめています。(TSHの基準値を、年齢や状況によって変えて評価することがポイントです。)
潜在性甲状腺機能低下症(全人口の4%前後、高齢者では5~6%)の治療について
- 妊婦の方:すぐに治療開始(TSHが通常の基準内値ではあるが妊婦基準値の5μU/mLよりも多ければ治療開始)
- 妊娠を考えている女性:条件付きで治療開始する
- 以上どちらでもない場合:まずは、一過性でないか、他の原因によるTSH上昇でないかなどを確認する
ヨード(ヨウ素)制限や疑われる薬剤中止を行って4~12週後に再検査する。
TSH値、動脈硬化性心血管疾患や心不全リスクの有無、自己抗体の有無、年齢(75~80歳を境として区別する) などを考慮して治療開始する。
問題点として、潜在性甲状腺機能低下症を放置した場合に認知機能低下・虚血性心疾患・心不全のリスクがあるかどうかは重要であるが結論が出ていない。 としています。
潜在性甲状腺機能亢進症(全人口の1~2%)については、
- 原因を検査確認する
- 一過性でないかどうかを確認する
- 持続性で外因がない場合は、TSHの値、年齢、心疾患・骨粗鬆症・甲状腺機能亢進症状の有無などにより治療開始するかどうかを決める。 としています。
以上のまとめや他の書籍での方針、甲状腺専門外来の先生方の御意見などを参考にして診療をすすめたいと思っています。
※話はかわりますが、インフルエンザに罹らないようにする工夫として(あるテレビ番組出演医師が同じ内容を発言されていましたが) ①自分の顔(眼・鼻・口)を触らない ②鼻を冷やさない(マスクなどで被う)を実践してきました。急患センター出務をしていた時には冬季に3時間で20~30人のインフルエンザ患者さんの診療をしていましたが罹患しませんでした。マスク・手洗い・うがいのみで上記を忘れると罹ってしまいます。
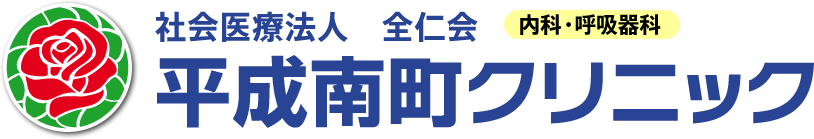
平成南町クリニック 玉田
 そこで、連休明けから「拡声器」を使用しています。(写真左下にある黒い器具がそうです。ネット注文送料込みで3980円) ハンズフリーで普通の大きさ・普通の口調で話しても「聞こえています。」と言っていただけます。
そこで、連休明けから「拡声器」を使用しています。(写真左下にある黒い器具がそうです。ネット注文送料込みで3980円) ハンズフリーで普通の大きさ・普通の口調で話しても「聞こえています。」と言っていただけます。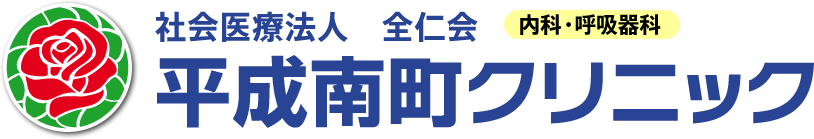


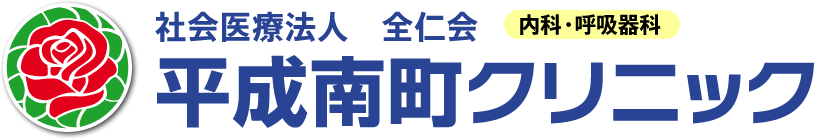

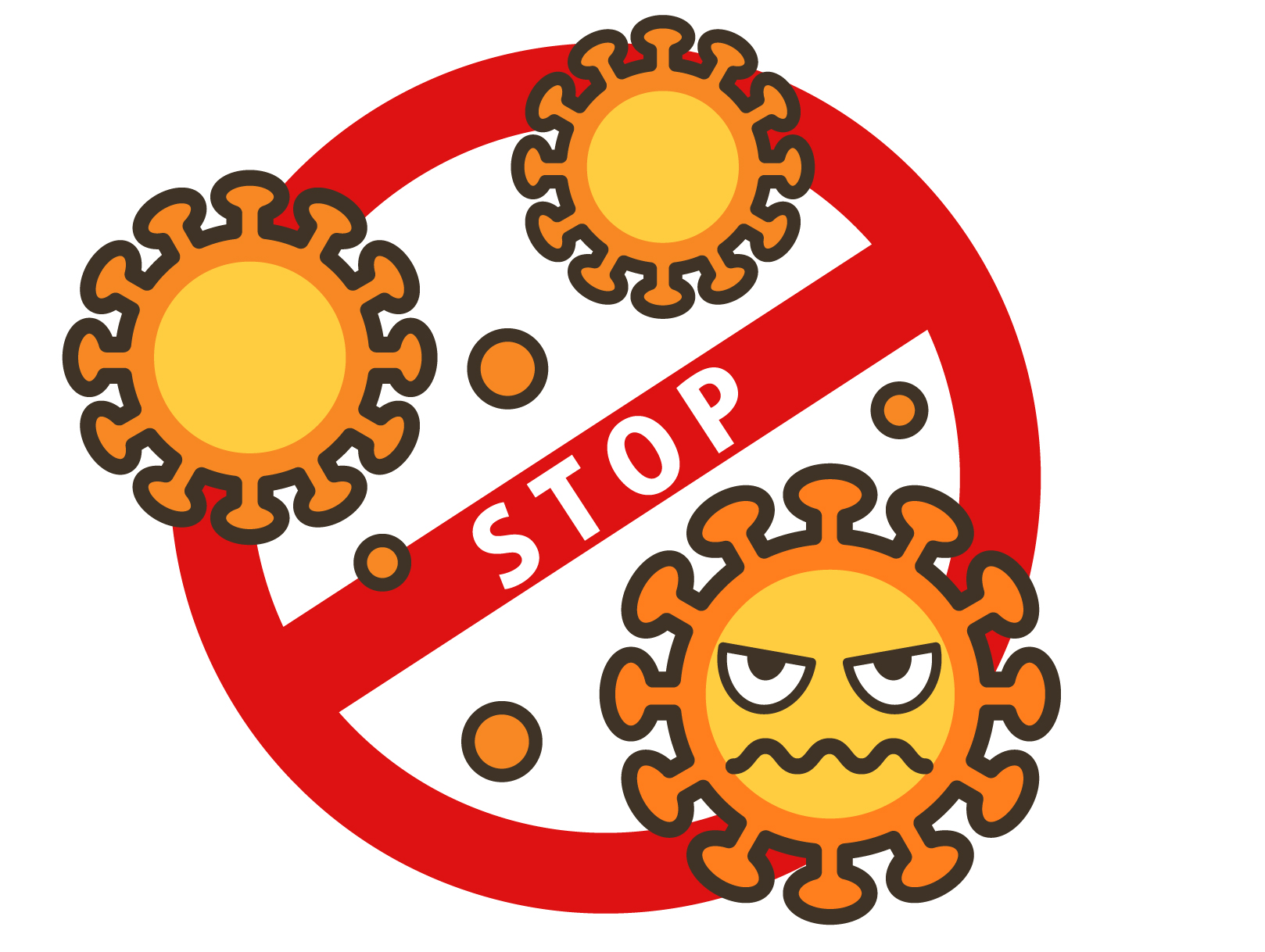
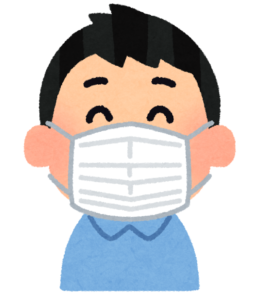
 1月14日にNKH本局ディレクターT氏の電話取材を受けました。番組「あさイチ」で昆布をとりあげるが、摂り過ぎによる甲状腺機能低下の可能性について調べている時に、2015年10月20日投稿の当ブログの記述を見つけたからとのことでした。(
1月14日にNKH本局ディレクターT氏の電話取材を受けました。番組「あさイチ」で昆布をとりあげるが、摂り過ぎによる甲状腺機能低下の可能性について調べている時に、2015年10月20日投稿の当ブログの記述を見つけたからとのことでした。(