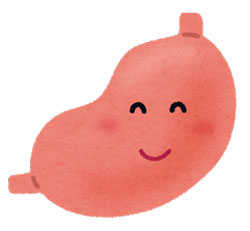今年は戌年ですね。「戌」の意味は植物などが枯れて休息をとる時期を表し、命を繋ぐ縁起の良い年を意味しているそうです。方角や時刻を意味する「戌」の読みがイヌなので、同じ読みの犬を宛てて「犬年」とすることも多いですね。さて、犬と言えば我が家では5歳の柴犬を飼っていて毎日癒されて暮らしています。しかし、柴犬に咬まれてしまう事例が、夏井 睦先生が主催されているサイトの「新しい創傷治療」の治療症例として度々登場しています。犬や猫に咬まれた時の傷の手当てについて夏井先生が工夫されている方法を以下に紹介します。
咬傷の傷口は普通小さく奥が深い傾向があります。犬や猫(ヒトもそうですが)の口の中には雑菌が多くいて、咬まれた傷は必ずそれらの菌で汚染されています。傷口が塞がってしまうと傷内部で菌の繁殖が進み治りにくい感染を成立させてしまいます。場合によっては血液中に菌が侵入して命を失うこともあります。
治療の原則は傷の中の浸出液を外へ出してしまうことです。洗浄し縫合して抗生物質で感染予防をしたくなりますが、適切な方法ではありません。傷口を閉じないようにし、且つ中の液体を外に出す(ドレナージと言います)ようにする必要があります。
傷の中に異物(ゴミやかけら)があれば取り出し洗浄(水道水で十分です)します。そして縫合用のナイロン糸を2本~数本束ねて折り曲げ「Uの字」の下の方を傷の中に入れます。糸の両端がほつれない様にテープで束ねておき、傷口の近くで糸の束を皮膚に貼り付けます。この時に絆創膏などで直接貼り付けると糸が抜けてしまう事が多いので、次の方法で貼り付けます。まず傷口のすぐ近くに、1×2cm位の大きさに切ったハイドロコロイド包帯を貼り付けます。そして糸の束をもう一枚のハイドロコロイド包帯で挟むように貼り付けます。こうすると1週間以上糸は抜けずに固定できます。もっともこのナイロン糸ドレナージを必要とするのは3日~数日間です。炎症が治まって感染徴候(腫れ・発赤・痛み)が無ければ糸を抜き取ります。ガーゼをリボン状にしたものを傷内に入れておくドレナージ方法もありますが、傷口部分が乾いて蓋になっている場合が多いので不適切です。傷口は浸出液を吸い取りかつ傷に固着しない被覆材(プラスモイストなど)で密封しないように被います。
この間、できれば抗生剤を内服します。どのような抗生剤を使用するかは、侵入したであろう菌の種類を考えて決めますが、咬傷の場合は嫌気性菌にも効果のあるラクタマーゼ阻害剤とペニシリン剤の合剤を使用することが多いです。免疫低下があると考えられる受傷者にはマクロライド系抗生剤を併用することもあります。
咬傷で問題とすべき細菌は以下のものがあります。
○コリネバクテリウム・ウルセランス 猫が多い 犬もある ジフテリアに近似(ジフテリア菌=コリネバクテリウム・ジフテリア) 抗菌薬→マクロライド系(エリスロマイシン、アジスロマイシン、クラリスロマイシン)、アミノベンジルペニシリン(つい最近の報道:屋外で野良猫に餌を与えていた60代女性で救急搬送3日後に死亡)
○パスツレラ・マルトシーダ 猫に多い 犬もある 抗菌薬→オーグメンチン(臨床検討例:70代女性。入院2日前に下腿打撲部を犬が舐めた。1日前に発熱・打撲部色調変化・水疱。入院翌日死亡)
○パスツレラ・カニス 犬に多い 抗菌薬→オーグメンチン
○エイケレナ・コロデンス ヒトに多い 抗菌薬→オーグメンチン
○バルトネラ・ヘンゼレ 猫に多い 猫ひっかき病の原因菌のひとつ 抗菌薬→アジスロマイシン
○カプノサイトファーガ・カニモルサス 犬・猫 「昨日元気で今日ショック」の場合の病原体の1つ 抗菌薬→オーグメンチン
○他のカプノサイトファーガ属菌 6種 内5種はヒト口腔内に存在 抗菌薬→オーグメンチン
平成南町クリニック 電話086-434-1122
平成南町クリニック 玉田