以前にも紹介しましたが、産婦人科医の宗田哲男医師の研究によれば、胎児のエネルギー源はブドウ糖ではなくケトン体です。胎盤には高濃度のケトン体が含まれていますが、ブドウ糖は胎盤にも臍帯血にも多くは含まれません。このケトン体は母体からの脂肪酸を原料として胎盤で作られています。胎児に必要な栄養素とするために母体には中性脂肪とコレステロールが増加しています。卵生動物の卵は蛋白質と脂肪でできていて、炭水化物(糖質)は殆ど含まれません。哺乳類の胎児も同じようにブドウ糖は殆ど必要としないのです。妊娠母体の血糖値が上昇しているのは、胎児がブドウ糖をより必要とするからではないのです。
宗田医師は次のような仮説を唱えています。(光文社新書 宗田哲男著 「ケトン体が人類を救 う」 )
う」 )
妊娠糖尿病は、妊娠母体が「糖質を拒否」している病態である。同時に「タンパク質と脂肪を要求」している。
(それなのに)これに気付かずに、妊婦が糖質過多の食生活を送るために、病気が発症してしまう。
そして、この仮説をもとに糖質制限食でインスリンを使用せずに、妊娠糖尿病・妊娠中の明らかな糖尿病・糖尿病合併妊娠の妊婦さんを治療し、健常な胎児を出産される方々を増やしておられます。
糖尿病学会のガイドラインでは糖質エネルギー比率60%が良いバランスとしていますが、これの根拠となる論文やエビデンスはなく、糖質過多の状況なのです。その食事でカロリー制限をしても妊娠糖尿病の妊婦さんは食後高血糖になります。ガイドライン通りのカロリー制限をすれば、胎児に必要なタンパク質と脂質を犠牲にしていることになります。(ドクター江部の糖尿病徒然日記2017年3月14日記載事項抜粋)
低糖質食にすると結果的に血中ケトン体が増加しケトーシスになりますが、これをインスリン不足時に生じるケトアシドーシスと同一視して「ケトーシスが危険」と考えてはいけないのです。胎児はまさにケトーシスの状態でスクスクと育っていくのです。また、新生児も脂肪含有量の多い母乳からケトン体を生成し脳の重要なエネルギー源にしています。(ヒューマン・ニュートリション第10版2004年) 小児も成人も脳はごく普通にケトン体を利用できるのです。(ドクター江部の糖尿病徒然日記2017年3月12日記載事項)
これまでの常識が「代わりの事実」のこともあります。「真の事実」は何かを問う姿勢を続けたいものです。
平成南町クリニック 玉田
「平成南町クリニック」カテゴリーアーカイブ
尿の電解質から判ること
血液(血清)中のナトリウムNa、カリウムK、カルシウムCa、マグネシウムMgなどの電解質異常がないかどうかは一般的検査として日常的に行います。異常値だった場合は、その是正が必要かどうか、原因は何かを考えて治療を行います。原因を追究することなくただ補正のみを行えばいいというものではありません。原因を区別する場合に役立つのが尿中の電解質です。また、高血圧治療の基本として食塩制限がありますが、1日に何グラムの食塩を摂取しているかを、尿のNa、クレアチニンCr、体重、年令から推定計算できます。
低Na血症の原因鑑別
まず尿浸透圧で区別しますが、尿のNa、K、尿素窒素BUN、Ca、Crで概算できます。
次に、尿Na濃度で区別して行きます。(最終診断には別の項目が必要です)
高K血症・低K血症の原因鑑別
腎臓からのK排泄量を評価することによって原因を絞り込むことができます。
尿のK、Crと 血清K、Cr、血糖、BUN を調べて計算します。
治療がうまく出来ているかどうかの評価にも役立ちます。
高Ca血症・低Ca血症の鑑別
正確には蓄尿でのCa濃度が必要ですが、原因の区別に役立ちます。
自尿の採れない場合には、導尿が必要になりやや侵襲的検査になってしまいますが、電解質異常の原因を考えながら治療する方がより早く治せるはずです。特に意識障害や脱力発作、重篤な不整脈などの緊急事態に際しては尿の電解質も是非調べましょう。
平成南町クリニック 玉田
メッケル憩室
本年1月9日(成人の日)、当院は倉敷市休日診療当番医でした。計29人の受診がありました。インフルエンザの疑いで18人にインフルエンザ゙迅速検査を行い16人がインフルエンザA陽性でした。(B陽性なし)。胃腸炎症状の方も複数おられました。他に、腹痛の訴えがあり診察にて胃腸炎ではなく腹膜炎が疑われる方が二人おられました。一人は虫垂炎疑いで消化器外科を紹介しましたが、虫垂炎を含む急性腹症はなく症状が軽快して帰宅されたとのことでした。
もう一人は高熱を伴い汎発性腹膜炎が疑われる方でした。当日の朝から右下腹部痛があり、自宅で様子を見ていたが嘔吐下痢はなく少量ずつ2回の排便もあったそうです。次第に腹部全体が痛くなり圧迫痛が出てきたので午後遅くに当院を受診されました。歩行時の腹痛増強はなくheel drop signは陰性でした。(つま先立ちをしてから踵をドンと着いた時に腹背部に痛みがあれば陽性) 腹部の緊張は強くなく柔らかく触れ腹膜炎を思わせない状況でした。しかし、腸の蠕動運動を示す腸音が殆ど聞こえず、tapping pain(指先で優しく叩いた時に感じる痛みで、あれば腹膜炎の疑いが強くなる)を腹部全体に認めました。また圧痛も腹部全体に認めました。来院時にも嘔気なく診察中も嘔吐・下痢はありませんでした。寒気は訴えておられませんでしたが38度の高熱であり、腹部全体の腹膜炎所見から汎発性腹膜炎で緊急対応が必要と考えられました。
腹部疾患の既往歴・手術歴なく原因が特定できない状況でしたので総合病院内科を紹介しましたが、すぐに外科転科となったとの連絡がありました。気になっておりましたが、緊急手術になったとの返事を1月11日に外科の先生から頂きました。メッケル憩室の穿孔による腹膜炎で、小腸部分切除を行い経過良好とのことで安心しました。
 メッケル憩室は、全人口の約2~4%の人に見られる最も頻度の多い消化管先天奇形です。胎生期に存在する卵黄嚢と中腸を結ぶ卵黄腸管が閉じずに残った場合にできる小腸(回腸)の憩室です。回盲部から50~100cm口側にあり症状なく経過することが多いのですが、時に腸閉塞、憩室炎、穿孔を起こして急性腹症として開腹手術になります。また出血・腹痛で慢性経過をたどる場合もあるようです。合併症は、小児では出血が、成人(50~60歳台に多い)では腸閉塞が多く男性に多い傾向があるようです。メッケル憩室自体を開腹手術なしで確定診断することは困難のようですが、詳細な画像検査を行い注意深く観察することで診断できるかもしれないとあります。合併症を予防するために無症状時に切除することは有意義ではないようです。
メッケル憩室は、全人口の約2~4%の人に見られる最も頻度の多い消化管先天奇形です。胎生期に存在する卵黄嚢と中腸を結ぶ卵黄腸管が閉じずに残った場合にできる小腸(回腸)の憩室です。回盲部から50~100cm口側にあり症状なく経過することが多いのですが、時に腸閉塞、憩室炎、穿孔を起こして急性腹症として開腹手術になります。また出血・腹痛で慢性経過をたどる場合もあるようです。合併症は、小児では出血が、成人(50~60歳台に多い)では腸閉塞が多く男性に多い傾向があるようです。メッケル憩室自体を開腹手術なしで確定診断することは困難のようですが、詳細な画像検査を行い注意深く観察することで診断できるかもしれないとあります。合併症を予防するために無症状時に切除することは有意義ではないようです。
今の季節は、高熱患者さんの多くはインフルエンザ感染が疑われますが、インフルエンザ迅速検査が陰性であればもちろん陽性であっても、他の緊急性疾患を見逃さないような診察が必要と実感しています。
平成南町クリニック 玉田
帆船ロンベルグ号をいかに操って長江を渡るか
謎解きのようなタイトルですが医学徴候の私なりの覚え方です。言葉を、場所を含む画像イメージとして憶えるのは記憶力が低下してきた場合にとても有効です。
今回は「ヘルニア」についてです。椎間板ヘルニア、食道裂孔ヘルニア、鼠径ヘルニアなどがありますが、比較的まれな「閉鎖孔ヘルニア」についてお話します。
骨盤腔の下方で坐骨・恥骨・腸骨に囲まれる三角形の空隙を閉鎖孔と言いますが、その中に閉鎖神経と閉鎖動脈が通る閉鎖管があります。閉鎖孔は骨盤腹膜と内・外閉鎖筋とで閉じられているのですが、そこが何らかの理由で緩むと閉鎖管の中に小腸(回腸)が入り込み、閉鎖孔ヘルニアとなります。(大網、卵巣、卵管、子宮などのこともあります) ヘルニア内容物によって閉鎖神経が圧迫されると、閉鎖神経知覚枝の分布する大腿内側、膝、股関節部に痛みや知覚異常をおこすのです。小腸が入り込むと、その程度が軽ければ下腹部の違和感や食欲不振を、通過障害を起こせば腸閉塞を起こして強い腹痛や嘔吐を生じます。
非常に頻度は低いとされていますが、過去4ヶ月で閉鎖孔ヘルニアの方を二人経験しました。
○93歳 標準体重の女性 既往 腰椎すべり症による脊柱管狭窄症
1年前から、腹部不快感や右大腿部の引きつけ感・しびれ・痛みがあるもしばらくすると自然に軽快することを繰り返していた。長時間の座位や歩行時に出現することが多かった。当院も受診されているが既往症による痛みを考えていた。
前日の夜に右大腿内側部が非常に痛く歩行困難となり救急外来受診。CT検査にて右大腿に著変なく帰宅。
翌日、痛みはやや軽減するも続くため当院受診。特徴的な痛みから右閉鎖孔ヘルニアを疑い前日のCTを見直したところ、右の外閉鎖筋の間に腸管構造を認め右閉鎖孔ヘルニアと診断した。
診断後の経過
C病院外科を紹介受診し1か月後に予定手術となったが、その後鎮痛薬を変更して痛みのコントロールが容易となり、腹部症状もなく経過したので本人希望で手術延期となった。
診断確定2ヶ月半後の深夜に右大腿部激痛あり救急外来受診。翌日未明午前1時45分にCT撮影し鼠径ヘルニア疑いで帰宅となる。同日午前9時30分当院受診。CT所見では右閉鎖孔に腸管が陥入し小腸浮腫所見あり、C病院外科に緊急手術を依頼した。翌日午前1時に緊急手術となった。(ヘルニア内容を還納し閉鎖孔をパッチで閉鎖) 術後は順調に経過し右大腿・下腿の痛みなく生活されている。
○86歳 BMI16.7の痩せた女性 心臓弁膜症あり
1年11ヵ月前 右下腹部から腰部にかけて激痛あり、翌日も鈍痛続き救急外来受診し腹部CT撮影。原因不明のまま帰宅。(今見直すと、両側の恥骨筋と内閉鎖筋の間隙が大きく開いており、大網が入り込んでいると思われる)
1年6か月前 10日前から右下腹部痛が持続し救急外来受診の朝に嘔吐あり。救急外来到着時には症状は軽減していた。CT所見は前回と同じで経過観察となっている。
診断日 起床して起座になった時に右臀部から右大腿上部にかけて強い痛みあり。起立すると痛みがさらに増強したので当院受診。数日前から食欲不振あり。力んでも排便なかったが緩下剤や浣腸を拒否されていた。
痛みの原因として右閉鎖孔ヘルニアを考えたが、食欲不振の原因精査を兼ねて全身CT検査を施行。
右閉鎖孔(恥骨筋と内閉鎖筋の間)に腸管構造と思われる索状物を認め、右閉鎖孔ヘルニアと診断した。腸管の変化を認めないので、腸閉塞を起こしうる危険性について説明し、緩下剤服用や浣腸施行して腹圧をかけないように指導した。その後は力まずに排便できるようになり、右大腿部痛は消失している。
お二人の経験から、閉鎖孔ヘルニアの症状は長時間の坐位や立位・歩行後、腹圧の高まる状況で出現しやすくなると考えています。ヘルニア内容は自然に元に戻ることもありますが、根治には外科的治療が必要です。日常生活に困る場合は待機的手術、イレウスを発症した場合には緊急手術が必要です。
最初の謎解きはこういうことです。Howいかに(操るか)ship(帆)船―Rombergロンベルグ(号) sign 徴候(長江)→Howship-Romberg sign =ハウシップーロンベルグ徴候。膝から大腿内側や股関節部に痛みがあり、大腿を後方へ伸展させたり、外側に拡げたり内旋(下肢を伸ばして足先を内向きに回す)したりすると痛みが増強する状態で、「閉鎖孔ヘルニア」の診断根拠となる徴候です。閉鎖孔ヘルニアによる下肢痛を坐骨神経痛などの整形外科的疾患と見誤ることもあるので注意が必要です。痩せた高齢の女性に多いので、そのような方の下肢痛(特に大腿内側部痛)や腹部症状・イレウス症状をみた場合は、“帆船ロンベルグ号”を想い浮かべる必要があります。
今年の平成南町クリニック号の操舵はどうだったでしょうか。上手に操れば帆船は風上へ進むことができます。平成南町クリニック号も風上へ進みたいものです。(写真はローズガーデン倉敷のイルミネーションです)
平成南町クリニック 玉田
和みの空間
胃潰瘍や逆流性食道炎の治療に使われるPPI(プロトンポンプインヒビター)をご存じでしょうか。最近では胃のピロリ菌除菌治療に抗菌薬と併用されています。胃酸の分泌を抑えて胃液逆流の症状緩和や胃潰瘍・十二指腸潰瘍の治療に使用します。よく使う薬の一つで重宝する薬です。
しかし思わぬ副作用が出る事があります。まだ経験していませんが、見過ごしているかもしれません。
慢性下痢症の原因になる顕微鏡的腸炎(膠原繊維性大腸炎やリンパ球浸潤性大腸炎など)、急な腎機能障害の原因になる急性間質性腎炎、神経症状や不整脈の原因になる低マグネシウム血症、精神症状を起こすことがある低ナトリウム血症 などです。
普段と違う症状や所見がある場合には、処方している薬剤全ての影響も考えなければならず、短い診療時間では把握しきれずに処方変更ができずにいるかもしれないと心配になります。それこそ「胃潰瘍」になってしまいそうです。
 そんな時は、なにか癒しが欲しくなりますが、我が家では柴犬(4歳雄)が私の帰りを待ってくれています。優しい気性でほっとさせてくれます。「柴犬ポスター」にしてクリニックに貼っていますが、「癒される~」と皆様に言って頂き好評です。(毎年作っています)
そんな時は、なにか癒しが欲しくなりますが、我が家では柴犬(4歳雄)が私の帰りを待ってくれています。優しい気性でほっとさせてくれます。「柴犬ポスター」にしてクリニックに貼っていますが、「癒される~」と皆様に言って頂き好評です。(毎年作っています)
癒しと言えばキャラクターグッズも役立ちますね。当院は、小児 科診療はしていませんが、熱傷や外傷で小児の患者さんも来られます。1~3歳の子供達は「何をされるのか分からなくて怖くて」泣いてしまうことも多いです。そこで子供達に興味のあるキャラクターグッズを少し用意しています。アンパンマン(大・小 手作り人形)、おさるのジョージ(アンパンマンでは効き目のない子供さん用)、指人形(新着 11月12日の職員旅行にて神戸イケアで購入)などです。機嫌を治して治療がスムーズに行くよう工夫しています。
科診療はしていませんが、熱傷や外傷で小児の患者さんも来られます。1~3歳の子供達は「何をされるのか分からなくて怖くて」泣いてしまうことも多いです。そこで子供達に興味のあるキャラクターグッズを少し用意しています。アンパンマン(大・小 手作り人形)、おさるのジョージ(アンパンマンでは効き目のない子供さん用)、指人形(新着 11月12日の職員旅行にて神戸イケアで購入)などです。機嫌を治して治療がスムーズに行くよう工夫しています。
来て下さる方々にとって、クリニックが和みの空間になるよう願っています。
平成南町クリニック 玉田
手指の単独麻痺
気管支喘息で定期的に受診されている方が、前日の夜7時頃から左手指の違和感と動かしにくさが起こり、朝になっても治らないと訴えて来院されました。視床梗塞に多い手掌・口症候群かと思いましたが口周囲のしびれはないとのことでした。めまいはなく顔や両手の痛覚障害はありませんでしたのでワレンベルグ症候群(延髄外側の梗塞)は考えにくい状況でした。しかし末梢神経障害にしては突然すぎる発症でしたので、何らかの脳梗塞と考え、倉敷平成病院脳卒中内科に紹介させて頂きました。
 MRI検査で右頭頂葉の小範囲の脳梗塞の診断で入院となり抗凝固療法が開始されました。数日後には、左手指の麻痺や異常感覚は消失し退院されました。
MRI検査で右頭頂葉の小範囲の脳梗塞の診断で入院となり抗凝固療法が開始されました。数日後には、左手指の麻痺や異常感覚は消失し退院されました。
この時は、そのような非常に限局した部位のみの脳梗塞もあるのだなという意識でした。しかし、「見逃し症例から学ぶ 神経症状の極めかた(平山幹生著 医学書院 2015年11月)」の中に、「50:一側の手指の脱力を急にきたした患者」のタイトルで上記の方と全く同じ状況の症例提示がありました。その症例提示では、右頸椎間孔が狭くなっていたので最初の診断は頸椎症性神経障害としたがMRI検査で「手指単独の麻痺(isolated hand palsy)」の診断に修正したという内容でした。
 isolated hand palsyは、脳の前頭葉の中心前回の一部でprecentral knobと呼ばれる部分の梗塞で起きるとされています。手指単独の麻痺は末梢性麻痺と誤り易いので注意が必要とありました。提示されているMRI画像所見は左右の違いはありますが受診された患者さんとほぼ同じ所見でした。
isolated hand palsyは、脳の前頭葉の中心前回の一部でprecentral knobと呼ばれる部分の梗塞で起きるとされています。手指単独の麻痺は末梢性麻痺と誤り易いので注意が必要とありました。提示されているMRI画像所見は左右の違いはありますが受診された患者さんとほぼ同じ所見でした。
急性の麻痺発症では小範囲であっても、まず第一に脳梗塞・脳出血を考えるということを改めて学びました。
写真は、若桜鉄道のある鳥取県八頭郡若桜町のスナップです。(10月9日に訪れました。)
若桜駅のSLと給水塔、カリヤ通りの仮屋(ひさし)、名物の豆菓子
平成南町クリニック 玉田
腎機能低下時の降圧薬
高血圧の治療薬でよく使用されるものに、RAS阻害薬があります。RASとはレニン・アンギオテンシン系のことでRAS阻害薬には、ACE―I(アンギオテンシン変換酵素阻害薬)とARB(アンギオテンシンⅡ受容体遮断薬)の2種類があります。どちらも最終的にアンギオテンシンⅡという昇圧物質の作用を低下させて血圧を下げる効果があります。2種類とも降圧薬としてよく使われる薬です。次いでよく使用される降圧薬は、長時間作用型Ca拮抗薬です。
腎臓の働きが低下するのを防ぐためには血圧の適正なコントロールが必要ですが、慢性腎臓病(CKD)の教科書には、一定の注意が必要だが血清Cr値※が高くてもRAS阻害薬が第一選択薬であり有用であるとなっています。長時間作用型Ca拮抗薬は血圧変動が大きい場合やⅢ度高血圧(180/110以上の高血圧)の場合には推奨されるとしてあり2番手の降圧薬の扱いになっています。![]()
当院の通院患者さんで元々腎機能低下があり長時間作用型Ca拮抗薬で血圧コントロールができていた方が経過中に高度の皮膚炎と好酸球増多を生じ、皮膚科の先生から降圧薬が原因かもしれないと指摘されました。Ca拮抗薬を中止してACE―I 薬で高血圧コントロールを行いました。皮疹や好酸球増多は改善傾向がみられましたが、腎機能がさらに低下し腎臓病専門医へ紹介して対応をお願いしました。降圧薬としては血管拡張作用のある長時間作用型Ca拮抗薬を中心に使用するのが良く、腎機能が低下してGFRが少ない場合にはACE―IやARBは使用しないようにとのアドバイスを受けました。
しかしながら、この患者さんはアレルギーのためCa拮抗薬が使用できず、α遮断薬、β遮断薬で血圧をなんとかコントロールしています。ACE―I 中止後には腎機能は軽度回復しました。皮疹や好酸球増多は数か月かけて改善しました。
他の腎機能の低下している患者さんでも長期使用していたACE―IやARBを中止して他の降圧薬に変更すると、腎機能を評価するeGFR値が若干改善することを実感しています。今後は腎機能低下のある高血圧患者さんへはACE-IやARBの投与を中止して他剤の組み合わせに変更していく計画にしています。
実診療専門医から見ると、教科書的な治療法が常識ではない場合があるものです。
※血清Cr値:Crはクレアチニンのことで、クレアチンの代謝産物です。腎臓の糸球体から濾過されて尿に出ていきます。腎機能が低下すると尿中への排泄が減り血液のクレアチニン値が増えます。クレアチンは筋肉収縮のためのエネルギー源であり運動により消費されてクレアチニンに変化します。従って作られるクレアチニンは筋肉量・運動量によって異なります。血清クレアチニン値を性別・年齢で補正して計算したものがeGFR(推算糸球体濾過値)です。
平成南町クリニック 玉田
貧血の方が良い?!
貧血の診断は、多くは血液中のヘモグロビン濃度(ヘモグロビンは酸素を運搬する血色素です)で行います。貧血は以下ように定義されます。(Hb=ヘモグロビン 単位はg/dLです。)
60歳未満 男性Hb 13.5未満・女性Hb 11.5未満
60歳~70歳未満 男性Hb 12.0未満・女性Hb 10.5未満
70歳以上 男性Hb 11.0未満・女性Hb 10.5未満
さて貧血の治療をいつ始めるのがよいか、目標とするヘモグロビン値はどれ位が良いのかについて次のような文章がありました。「極論で語る総合診療」 桑間雄一郎著(米国 マウントサイナイ・ベスイスラエル日本医療部門) 丸善出版 H28年6月30日発行 212頁~217頁。 AABB(アメリカ血液銀行協会)ガイドラインによれば、
集中治療室患者での輸血の目標はHb7~8g/dLが良い。
また、論文 Am J Cardio12 2008:102(2) 115-9 によれば、
急性心疾患:急性心筋梗塞においてはHb8g/dLを下回った場合に輸血する。となっているそうです。
いずれも「貧血」の基準値をかなり下回った時に治療を開始することになります。
現在用いられているヘモグロビン正常値(基準値)は、はるか昔の進化の過程で獲得した十分な備えとしての値であり、出血の危険や限界に近い運動の必要性があまりない安全な生活を送っている現代人にとっての目標値ではないと考えるのだそうです。
(血小板基準値は、13万/μL以上ですが安全な現代人にとっては2~3万/μLあれば十分とのことです。)
また、腎機能が低下して起こる腎性貧血の治療のエリスロポエチン製剤を使用する時のヘモグロビン値の治療目標は次のようにされています。
保存期慢性腎臓病(CKD)では、11g以上13g未満(重篤心血管系の既往・合併あれば12g未満)
高齢者では、13g以上にならないようにする(開始基準は10g/dL未満とする)
ヘモグロビン13.5g/dL以上の値そのものが危険因子になる(死亡・心筋梗塞・心不全入院・脳卒中罹患率)
非高齢男性の基準値がむしろ危険であると言うのは驚きです。
これらを総合すると、「ヘモグロビンが低下してきている原因を放置してはいけないが、慢性的に低い場合は少な過ぎない限りむしろ生命にとって有利かもしれない。」となります。
「貧血がありますよ。」と言う説明は、よほど深く考えてから行わなければならないと感じました。
平成南町クリニック 玉田
水辺のケガに注意
暑い夏がやって来ました。川や池、湖、海などの水辺で遊ぶのが楽しい季節です。でも皮膚に怪我をしていたり水辺で怪我をした後で皮膚が赤くなったり腫れて痛くなった時(軟部組織感染症)には、普段の怪我とは違う注意が必要です。
通常の軟部組織感染症(創感染・蜂巣炎・筋壊死・壊疽性膿瘡など)の原因菌はグラム陽性球菌のブドウ球菌、連鎖球菌ですが、海水・淡水(川や池・湖・プール・水槽)に触れる状況があった後で軟部組織感染症を起こした場合には、病原微生物として以下のようなグラム陰性桿菌を想定する必要があります。
エロモナス ヒドロフィラ(Aeromonas hydrophilia)
ビブリオ バルニフィカス(Vibrio vulnificus)
類丹毒菌(Erysipelotrix rhusiopathiae)
エドワードシェラ タルダ(Edwardsiella tarda)
緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)
ブドウ球菌や連鎖球菌感染には、第一世代のセフェム剤やペニシリン剤が適していますが上記の微生物には効果がないので、キノロン剤・ST合剤・ミノサイクリンの内服や第3世代セフェム剤の注射などを使います。
また頻度は低いですが、水との接触後の感染症として、抗酸菌の一種のマイコバクテリウム マリナム(Mycobacterium marinum)による皮膚感染症やスピロヘータの一種のレプトスピラによる全身疾患もありえます。沖縄・奄美諸島などでは現在でも水田などでの糞線虫感染(全身疾患で皮膚には蕁麻疹のような発疹)も報告されています。水関連感染症には、その他の病原体もあります。
海や川などに行った後で皮膚病変や風邪様症状などの全身症状が出た時には、水辺に特有な微生物の感染症を考える必要があります。
平成南町クリニック 玉田
以下などを参考にしました。
淡水との接触による感染症(週刊医学会新聞 2015年4月13日 Dialog & Diagnosis 第4話)
レジデントのための感染症診療マニュアル第2版767ページ
KANSEN journal No.46(2013.12.26)
STSTA 感染症の病歴
NHKのドクターGで、発熱と発疹という似た症状の3人のうち「ジカ熱」の人は誰かという番組がありました。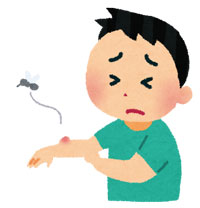 発熱と発疹の時間的関連と感染してから発症までの期間で区別するという内容だったと思います。番組では3人ともブラジルへの渡航歴があるという設定でした。
発熱と発疹の時間的関連と感染してから発症までの期間で区別するという内容だったと思います。番組では3人ともブラジルへの渡航歴があるという設定でした。
発熱の患者さんの場合、まず感染症かどうかを考えます。感染症と考えた場合にどの臓器への感染なのか、そうすると可能性の高い病原体は何かを推定します。病原体を推定する時に役立つのが病歴ですが、感染症の病歴を漏れなく確認するチェックリストの頭文字がSTSTAです。
Sick contact 発熱や似たような症状の人が周囲にいたか
TB contact 結核またはその疑いの人が周囲にいたか
Sexual contact 性的な接触歴の可能性があったか
Travel history (海外)旅行歴。国内でも森林に行った、素足で泥水に触れたなどの環境因子も含みます
Animal contact 動物との接触歴。人獣共通感染症(ズーノーシス)は数多くあります。
病歴を確認して可能性のある感染症のなかで眼の前の患者さんの症状や所見に合うものは何かと考えます。
その感染症に合わない症状や所見があれば可能性は低くなります。
ブラジルへの渡航歴があった発熱と発疹の人となると、ジカ熱・デング熱が問題になります。しかし他のSTSTAで他の疾患の可能性も考えなければなりません。ドクターGの3人の人は、それぞれジカ熱、デング熱、伝染性単核球症でした。
症状の経過は患者さん自身が詳しく話されますが、STSTAについてはこちらから質問しないと分からない事が多いです。聞き漏らしやすい内容を忘れないようにする「STSTA」をいつも念頭において診療するよう心掛けています。
平成南町クリニック 玉田

