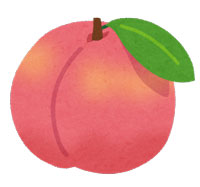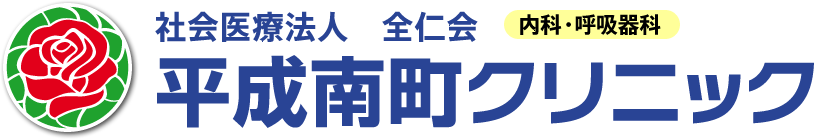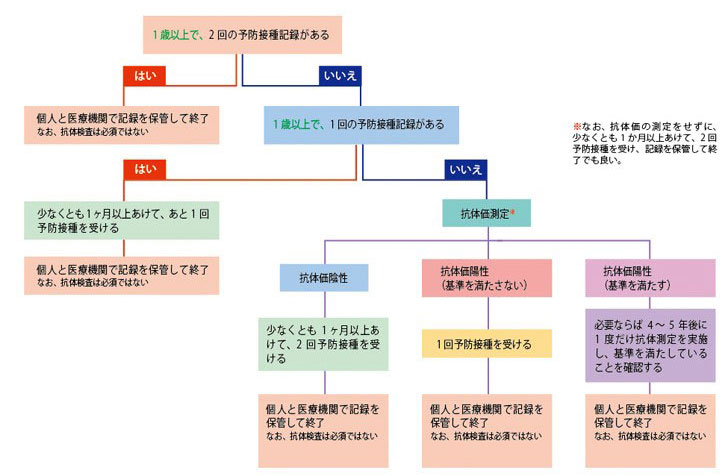蜂窩織炎(ほうかしきえん)を繰り返す患者さんがおられました。
倉敷平成病院の外来で免疫グロブリンの検査が行われ、選択的IgA欠損症と判明しました。IgAは粘膜表面(喉、気管支、腸)に存在して病原菌やウイルスの侵入を防ぐ役割があります。
原因の多くは遺伝性ですが薬剤の影響もあります。選択的IgA欠損症は、300以上の疾患がある原発性免疫不全症の内の1つです。
以下の10の徴候の1つ以上が当てはまる時は、原発性免疫不全症を疑う必要があります。(難病情報センター資料)
1. 乳児で呼吸器・消化器感染症を繰り返し、体重増加不良や発育不全が見られる。
2. 1年に2回以上肺炎にかかる。
3. 気管支拡張症を発症する。
4. 2回以上、髄膜炎、骨髄炎、敗血症や、皮膚膿瘍、臓器内膿瘍などの深部感染症にかかる。
5. 抗菌薬を服用しても2ヶ月以上感染症が治癒しない。
6. 重症副鼻腔炎を繰り返す。
7. 1年に4回以上、中耳炎にかかる。
8. 1歳以降に、持続性の鵞口瘡(がこうそう)、皮膚真菌症、重度・広範な疣贅(イボ)が見られる。
9. BCGによる重症副反応(骨髄炎など)、単純ヘルペスウイルスによる脳炎、髄膜炎菌による髄膜炎、EBウイルスによる重症血球貪食症候群に罹患したことがある。
10. 家族が乳幼児期に感染症で死亡するなど、原発性免疫不全症候群を疑う家族歴がある。
また、原発性免疫不全症では下記の感染症状が様々な組み合わせで見られます。(難病情報センター資料)
1.主に抗体産生不全によるもの
反復性気道感染症(中耳炎、副鼻腔炎を含む)、 重症細菌感染症(肺炎、髄膜炎、敗血症など)、気管支拡張症、膿皮症、化膿性リンパ節炎、遷延性下痢
2.主に細胞性免疫不全によるもの
遷延性下痢、難治性口腔カンジダ症、ニューモシスチス肺炎、ウイルス感染の遷延・重症化(ことに水痘)
免疫グロブリンにはIgAの他にIgG、IgM、IgD、IgEがありそれぞれに欠損・過剰時の疾患があります。
選択的IgGサブクラス欠損症ではIgG1、2、3、4の1つないし複数のサブクラスが欠損・低下します。
IgG2が低下すると莢膜を持つ細菌(肺炎球菌・肺炎桿菌・インフルエンザ菌・髄膜炎菌)の感染(中耳炎など)を繰り返しやすくなります。
選択的IgM欠損症では自己免疫疾患を合併しやすいと言われています。
IgD、IgEでは多すぎる時に発症する疾患があります。
感染症を繰り返す時には、後天性免疫症候群(AIDS)や薬剤、悪性腫瘍、脾臓機能低下、糖尿病、肝硬変などの続発性の免疫不全以外にも上記の原発性免疫不全症を考えておく必要があります。
意外と多いのかもしれませんが、鑑別診断は容易ではありません。疑いを持った時は、感染症科や血液内科の専門の先生にお願いすることになります。
平成南町クリニック 玉田
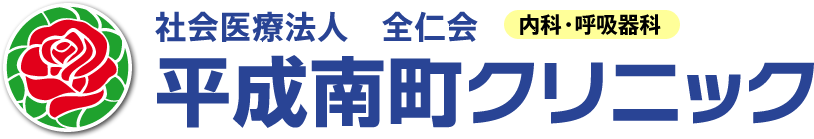
お知らせ
来年1月から平成南町クリニックの外来診療を一部変更いたします。
詳しくは倉敷平成病院HP案内欄の関連施設「平成南町クリニック」をご参照ください。