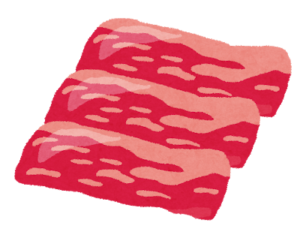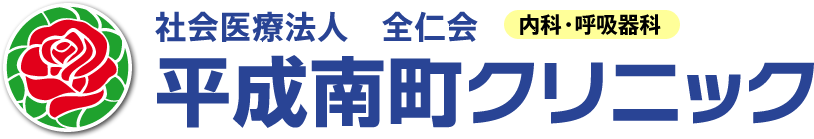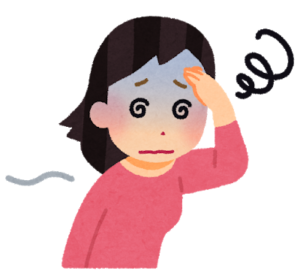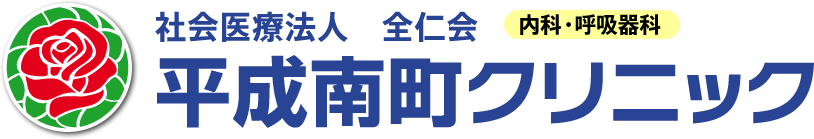風邪の季節になりました。風邪に罹って頭痛がすることはよくありますが、頭痛だけの場合には帯状疱疹も考える必要があります。2016年2月20日の本ブログにて「カミ隠しの頭痛」で皮疹のない帯状疱疹のことを書きました。帯状疱疹をおさらいします。
水痘に罹ると水痘帯状疱疹ウイルスは全身の後根神経節内に潜伏します。何らかのきっかけでこのウイルスが再活性化して神経細胞周囲のサテライト細胞内で再度増殖することがあります。ウイルスは知覚神経を通って表皮に達し表皮細胞に感染するので赤い丘疹や水疱が形成されます。この皮疹は皮膚の神経分節に一致して(複数の神経分節のこともあります)見られるのが特徴的です。最初は紅斑で次いで実質性丘疹となりその後水疱を形成します。水疱がさらに膿胞や血疱になることもあります。
皮疹が出現する数日前から皮膚の神経分節に一致した神経痛様の痛みが起こることが多いのですが、この時期に帯状疱疹だと診断することは困難です。また皮疹が出現しないまま経過する帯状疱疹(無疱疹性帯状疱疹)もあります。帯状疱疹の治療は合併症を防ぐためにも出来るだけ早く治療を開始した方が良いのですが多くは典型的な皮疹の出現後に治療が開始されます。
皮疹出現前の帯状疱疹あるいは無疱疹性帯状疱疹を診断して治療を開始するにはどうすれば良いのでしょうか。水痘に罹患していないと断言するのは不可能に近いので水痘に罹ったことがあるとして考えます。
 1.本当に皮疹がないかどうかを確認する 毛髪に隠れている皮疹 外耳道の発赤・皮疹を確認する
1.本当に皮疹がないかどうかを確認する 毛髪に隠れている皮疹 外耳道の発赤・皮疹を確認する
2.帯状疱疹の痛みの特徴を知っておく
皮膚の神経分節(知覚神経枝の分布している範囲)に一致した部位の痛み
神経痛様の痛み チリチリした痛み アロデニア(異痛症)に似た痛みで、風が吹いても痛い 服が触れても痛い 電気が走る 焼けるような痛み(当院の患者さんで髪の毛を触っただけでとても痛いと表現された方がありました)
時には知覚鈍麻もあるので注意
3.痛み以外の帯状疱疹罹患時の合併症の症状や所見を知っておく(※※ 国立感染症研究所 帯状疱疹ワクチン ファクトシート 2017年2月10日)
4.皮疹の出現がない時やまだ出現してない時期に帯状疱疹と確定できる診断方法を知っておく。
眼部:目の擦過液、涙液 PCR、耳介擦過液PCR、唾液PCR
ペア血清IgM抗体 皮疹出現日の4~5日後から上昇し始める、無疱疹帯状疱疹では、痛みや皮膚違和感出現後から6~8日後から抗体上昇する
痛みや異常感覚を「帯状疱疹かもしれない」と考えて他の原因が明らかでない時には、抗ウイルス薬を開始してもよいのでしょうか? 早期に開始すると診断不能になるでしょうか?(典型的な皮疹が出なくなる? PCR偽陽性になる? 抗体価が上昇しなくなる? この点については当ブログ記載時点では明らかにできませんでした。)
ドクターサロン57巻10月号(2013年)にて、東京慈恵会医科大学皮膚科講師 松尾光馬先生は、「一般診療所では40%医師は、発疹を待たずに抗ウイルス剤を投与している。」と発言されています。
皮疹出現前の「無疱疹帯状疱疹」を治療する場合も皮疹出現後の帯状疱疹と同じで、抗ヘルペスウイルス薬(ウイルス遺伝子合成を阻害)の内服です。
腎排泄剤 3種類 ①アシクロビル(他2剤に比べ急性期疼痛・帯状疱疹関連疼痛の消失までの期間が長い) ②パラシクロビル ③ファムシクロビル
胆汁排泄剤1種類 アメナメビル(腎機能考慮不要 RFP等代謝経路同一薬剤併用は禁忌・要注意)
さて、帯状疱疹に罹らない事が最も重要ですが、その為にはどうすれば良いでしょうか。
(1)水痘に罹らないように小児期に水痘ワクチンを接種しておく。(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)
2014年10月予防接種法に基づき水痘ワクチンの定期接種が導入されました。その結果、2015年以降小児水痘患者は大幅に減少しています。しかしこのことで、周りの成人は水痘帯状疱疹ウイルスに曝露することが減少しています。結果として既感染者の再活性化(再発としての帯状疱疹)が増加すると推測され、実際に帯状疱疹患者が増加してきています。
(2)追加免疫のため帯状疱疹ワクチンを接種する。
「シングリックス」 不活化ワクチン 0.5mL筋肉注射 2回
(2018年3月23日に日本での製造販売が承認されましたが、製剤供給不足でまだ使用できません。)
「小児用の水痘ワクチン0.7mL皮下注射」を0.5mL皮下注射1回接種する(帯状疱疹予防明記あり)
(3)水痘帯状疱疹ウイルスの再活性化を防ぐ
水痘帯状疱疹ウイルスへの細胞性免疫の低下で再活性化するので、疲労 ストレスを避ける、他疾患で免疫抑制状態(糖尿病悪化・腎不全など)にならないようにする。
加齢による再活性化は防ぎようがありません!
(4)水痘帯状疱疹ウイルスに対する感染対策(※感染対策メモ)を知っておく。
帯状疱疹の合併症を防ぐためにも、一刻も早い診断ができるよう努力していきます。
(水疱出現後や合併症出現時の対応は、今回は割愛します。)
平成南町クリニック 玉田
※感染対策メモ
帯状疱疹の水疱中にはウイルスが存在しているので、接触感染を起こしえます。
水痘と同じように空気感染も起こしうるので、水疱部は被覆しておく必要があります。
水痘帯状疱疹ウイルスに免疫のない人へは20%感染起こすと言われています。
免疫異常のない帯状疱疹患者さんでも唾液中にウイルスDNAが検出され、時にウイルスも分離されます。
全身播種型や免疫低下状態の帯状疱疹患者さんへは、空気感染対策が必要です。
※※ 帯状疱疹合併症(国立感染症研究所 帯状疱疹ワクチン ファクトシート 2017年2月10日)
皮膚細菌性二次感染症(全ての知覚神経節)
帯状疱疹後神経痛(全ての知覚神経節)
眼合併症(第2、3、5脳神経第1枝多い=三叉神経第1枝:顔神経) 鼻尖部や鼻背部に帯状疱疹時に多い
角膜炎 上胸膜炎 虹彩炎 結膜炎 ブドウ膜炎 急性網膜壊死 視神経炎 緑内障
進行性網膜外層壊死 AIDS患者で認める
無菌性髄膜炎(第5脳神経) 頭痛 髄膜刺激症状
血管炎(脳炎) (第5脳神経) 髄液検査で診断30人中37%は皮疹なし 免疫不全者で多い
脳血管炎 昏迷 痙攣 TIA一過性脳虚血発作 脳梗塞
Bell麻痺(第7脳神経) 片側性顔面神経麻痺
Ramsay Hunt症候群(第7脳神経膝神経節と第8脳神経への拡大) 耳介・外耳道・舌前2/3の帯状疱疹
耳痛 めまい 舌前方のしびれ 顔面神経麻痺(皮疹に先行 皮疹ないのままもある)
聴覚障害(第8脳神経) 難聴
運動神経炎(全ての知覚神経節)筋力低下 横隔神経麻痺 神経陰性膀胱 排便障害 (腸閉塞もあった)
横断性脊髄炎(脊髄神経節) 麻痺 知覚麻痺 括約筋障害
内臓播種性VZV感染症 皮疹に先行して体内臓器感染(再活性化)で激しい腹痛・腰背部痛、肺炎・肝炎