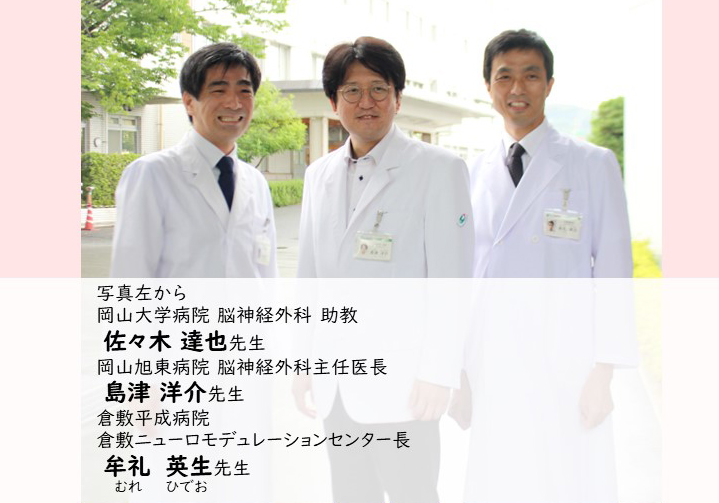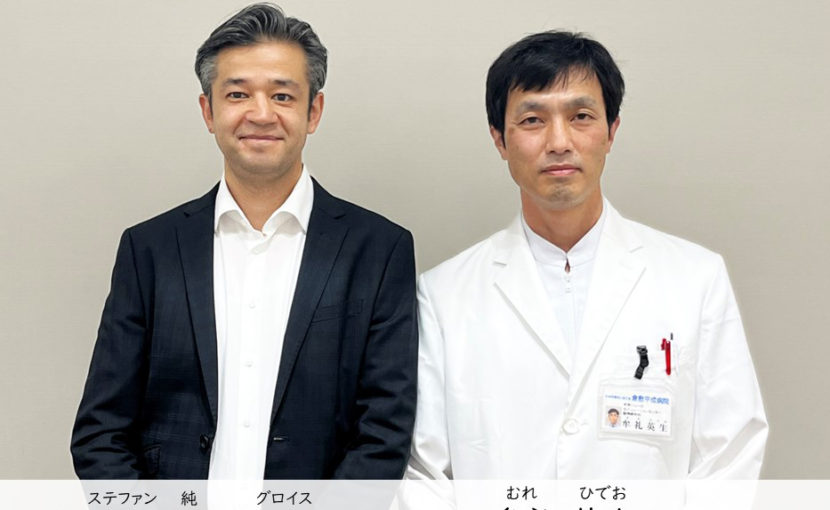認知症はパーキンソン病に合併しやすい疾患と言われています。
当院のニューロモデュレーションセンターでDBSの治療をお考えの方、治療中の方にはST(言語聴覚士)とCP(臨床心理士)が関わらせていただきながら定期的な評価をしています。
具体的には、認知機能評価、前頭葉機能評価、その他の高次脳機能評価として注意力・記憶力・遂行機能力を評価するテストを行っています。評価するタイミングはDBSの術前評価で手術を安全に行える認知機能を有しているかの確認と、手術後の3ヶ月後・1年後・電池交換の際に同様の検査を行い、機能が保たれているか確認をします。そして万が一に認知機能の低下が進んでいる・・・などの気になる症状があれば、患者さまに合わせた脳トレのやり方の指導もさせていただいています。

言語聴覚士
M.W