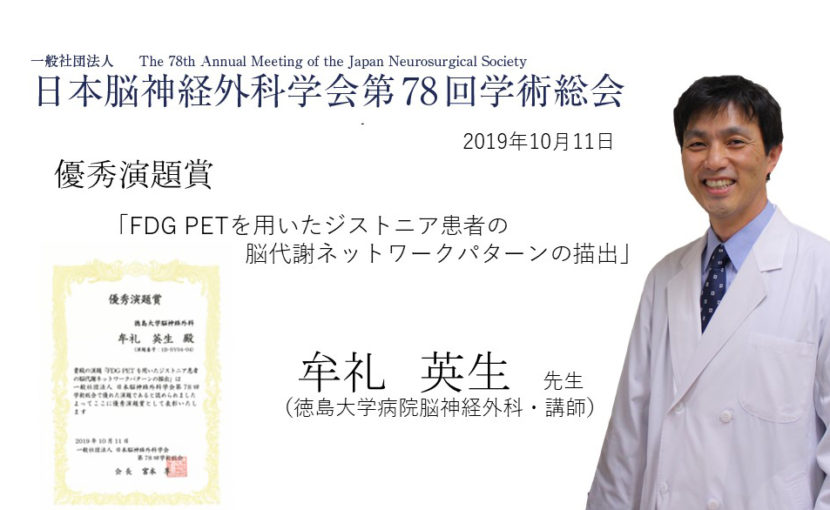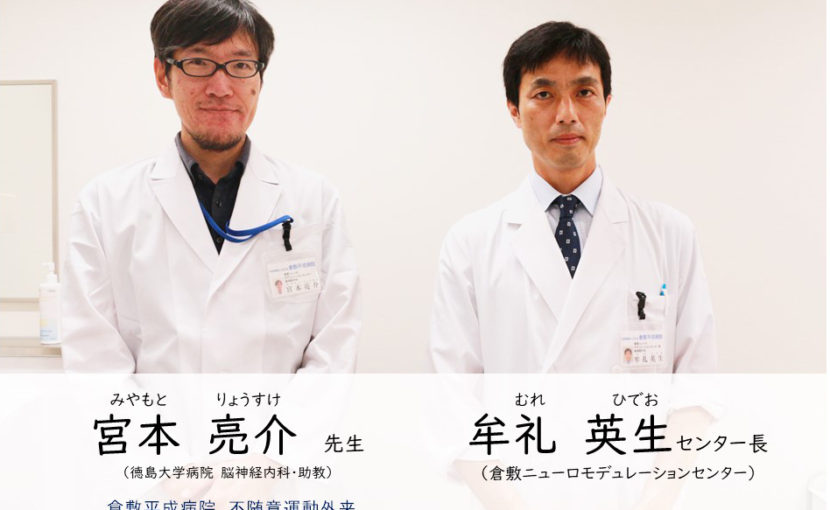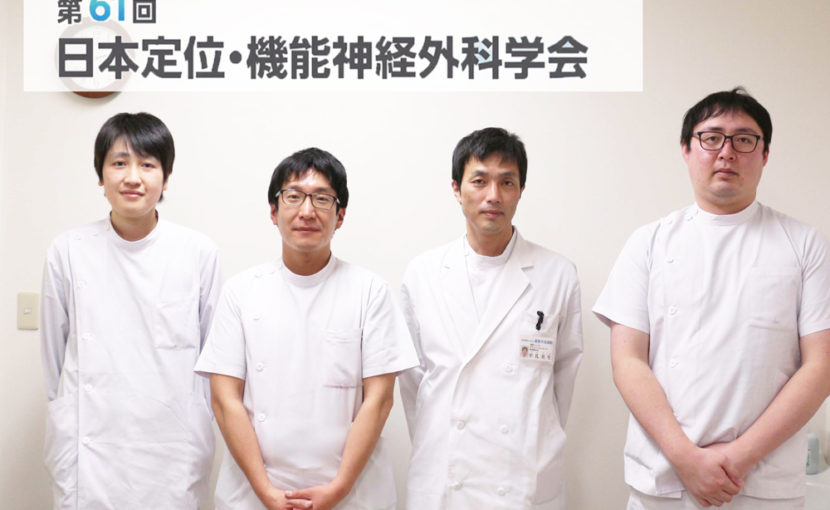ジストニアとは、筋肉の緊張の異常によって様々な不随意(自分で制御できない)運動や肢位、姿勢の異常が生じる状態をいいます。
症状は筋肉の異常収縮によるものですが、筋緊張を調節している大脳基底核という部分の働きの異常や上部脳幹、小脳など中枢神経が集まる部位において何らかの障害が起こるためと考えられており、緊張する筋肉の場所によってさまざまな症状を引き起こします。
• 首が曲がってしまう(痙性斜頚)
• 字が書きづらい(書痙)
• 声が出しづらい(痙攣性発声障害)
• 話すときに舌が出てしまう(口舌ジストニア)
このような症状がみられる中で、今回は痙攣性発声障害についてお話します。
痙攣性発声障害には、2つのタイプが存在しており、内転型と外転型のタイプに分かれます。90%以上は内転型であり、声門閉鎖筋の不随意収縮による声門の過閉鎖が原因で、声を出そうとすると声がつまる、声が震えるなどの症状が起こり、苦しく絞り出すような声になったり、息漏れ声、かすれ声になる場合があります。
外転型は、声門開大筋の不随意収縮による声門の開が原因で、ある音で声が抜けて息だけになったり、かすれたりする症状があります。特に言葉の始めの「さ行」「は行」などに多くみられます。
どちらも声帯そのものには異常がないことが多く、耳鼻咽喉科医の診察でも診断がつかないことがあります。
内転型のリハビリの方法として様々な方法がありますが、代表的な方法を挙げます。
・ 発声と呼吸のパターンを整えて努力性発声やスムーズな発声を誘導するための腹式呼吸
・ 喉頭筋の過緊張を軽減するためのあくび・ため息法や喉頭リラクゼーション法
当センターで行われているジストニアの治療には、薬物療法、DBS治療(脳深部刺激療法)、熱凝固療法(定位的脳手術)等があります。
言語聴覚士は、症状の改善と日常生活でのスムーズなコミュニケーションの実現をサポートするため、多角的に音声評価行い、それぞれの症状に合った訓練法や発声方法をアドバイスを行っています。
もし発声で気になることがあれば、お気軽にご相談ください。